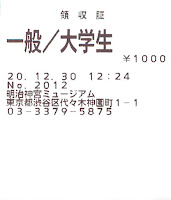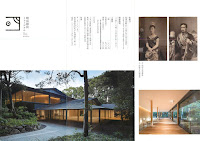● 今週末も2日間とも東京に出かける予定。今日は用あって練馬の光が丘に行く。 宇都宮線の車中。車内の広告で一番多いのは脱毛のやつ。色々ある。男性宛てのもある。どういうこと? 流行っているのか,流行っていたのにこのコロナ禍でカモが激減しちゃってるのか。
週刊誌の中吊りなんて,まったく見かけない。中吊りを見れば読む必要なし,と言われた時代は遠くへ去った(念のために申さば,完全に消えたわけではない。残っているものもある)。
● 自治医大駅で下車して,「休日おでかけパス」を購入。明日の分も買った。今日よりも明日の方が,休日パスが活きるはずだけども,JRで首都圏を移動するにはこれは便利。自治医大駅で降りるんだから1本遅れるわけだけど,これはそうしてでも買っておいた方がいいでしょう。 自治医大駅のホームから冬の空を眺めてみる。寒いけど,確実に春を孕み始めている。
● 湘南新宿ラインで池袋。ここからメトロ副都心線に乗り換えて,地下鉄赤塚駅で降りる。板橋区と練馬区の区境にある。東京都下でもいたって地味なエリアと言ってよろしかろう。
光が丘の最寄駅は都営大江戸線なのだが(光が丘駅は大江戸線の終着駅),今回は赤塚から約2キロを歩いてみようと思う。
● 赤塚駅を上がって地上に出ると,川越街道。そこを渡って次の細い道を東に向かう。と,いたってスムーズに動けたように書いているけれども,これは後から地図を見ているわけで,現地では行きつ戻りつがあったのは言うまでもない。ぼくは方向音痴を辞任している。現地でどっちが東かなんてのはわからない。
とにかく東に行くと,“ゆりの木” という団地群が現れる。ゆりの木商店街があり,ゆりの木児童館があり,ゆりの木保育園がある。小さい子を連れた母親がゆっくり歩いていたりする。
● が,商店街(道の両側に商店が並んでいるのではないのだが)にさほどの活気は感じなかった。20年後,30年後にはこのあたりはどうなっているだろう。高島平や多摩ニュータウンを見るにつけ,人工的に拵えた住宅街はあまり長い寿命を持たないものであることがわかる。
いや,奈良の飛鳥をはじめ,かつて栄華を誇ったであろうところが,今は何もないただの田舎になっている例はさほどに珍しいものではない。栄枯は移るのであるけれども,人工度が高いところは短期間で移り変わる。
● ということをツラツラ思いながら,歩いていると,光が丘公園に至る。景観も都会成分が濃くなってくる。何より,一気に人が増える。 代々木公園には及ばないけれども,かなり広い公園だ。公園内に野球場もテニスコートも陸上競技場もある。
老若男女が思い思いに繰りだしている。コロナの緊急事態宣言が出ていることを忘れさせる。
銀座や日本橋は,そこに住んでいる人はそんなに多くはなく,よそからやって来た人たちが賑わいを作りだす。したがって,緊急事態宣言が出ると,その賑わいが面白いように消失する。 が,ここはそうではない。ここに住んでいる人たちが集まっているのだ。緊急事態宣言が出ようがどうしようが,他に行くところはない。ここに来るしかない。でなければ,本当に家の中から出ないでいるほかはない。
● 光が丘公園を横断というのか縦断というのか,要するに横切って南に出ると,そこが光が丘の中心部。都営大江戸線の光が丘駅があり,大きな病院があり,ショッピングモール(光が丘IMA)がある。高層住宅の建物がニョキニョキと生えている。
そのショッピングモールにも人が多い。食堂やレストラン,ファストフード店にも行列ができていたりする。銀座や日本橋とはやはり様相を異にする。
● 大江戸線に乗って東中野でJR線に乗り換えた。大江戸線は新宿まで行くので,新宿で乗り換えればいいようなものだが,新宿で乗り換えるのは億劫だ。
新宿から山手線に乗り継いで渋谷に行って見ようと思っているので,どっちにしたって新宿で乗り換えるんだけども,JR駅の中ですむのと,地下鉄の新宿駅からJRの新宿駅まで動くのとでは,田舎者にしたらかなり違うのだ。
● なぜ渋谷に行こうと思ったかというと,渋谷LoFtを覗いてみたくなったからだ。渋谷LoFtには過去に二度来ているし,それ以外でも渋谷には何度も訪れている。いくらぼくでも,さすがに。
しかし,東京で最も苦手な場所は渋谷だ(新宿には慣れてきた)。とにかく人が多い。今日も普段よりは少ないのだろうけど,それでも人酔いする。
もうひとつ,地理が飲みこめない。道玄坂とセンター街と文化村通り。そりゃ,地図で見ればなるほどこっちが道玄坂でここがセンター街かとわかるけれど,現地にその地図をあてはめるのに難渋する。だから渋谷という。
● ハチ公口を出て,ニッチもサッチも行かなくなるのだ。たとえば,ここから渋谷LoFtはわずかの距離だ。それでも,行くときは最短距離で行けたのに,帰りに迷ってとんでもなく遠回りを強いられたことがある。
そういう思いをしたのだから,次からはパッと行けるかというと,そういうふうにならない。
● ハチ公前で,マスクはするなと街頭演説をやってるグループがいた。しかも,若い人たち。
歳を取るとバカが先鋭化するから,ジジイやババアがやってるならまだわかるんだけどね。
若いんだから,人のことなんか構ってないで,自分の人生に集中しなよ,と思ったことであったよ。
● どうしてそんな余計なことをするのかといえば,暇だからだよねぇ。小人閑居して不善を為す,の類なんだよね。
バカには忙しくさせといた方がいいんだよ。暇なんて贅沢なものを与えちゃいけないんだわ。・・・・・・あぁ,忙しい,忙しい!!
● 渋谷から山手線に乗って,品川まで来るとホッとする。池袋~新宿~渋谷の湘南新宿ライン文化圏から上野東京ライン文化圏に出たからだ。
「ふるさとの訛なつかし停車場」の趣を湛えているのは上野東京ラインの方だ。宇都宮からJRで東京に出る場合,ついこの間までは必ず上野で乗り換えることになっていた。東北や北関東から上京するときは,上野がターミナル駅だった。「くじけちゃいけない,人生は」と励ましてくれる「おいらの心の駅」であり続けたのだ。湘南新宿ラインはアウェイなのだ。
● 上野東京ラインの開通以来,それまで上野駅が持っていたターミナル機能は新橋駅にそのまま移行された。ぼくの場合は,だけど。
東京駅のように大きすぎない。銀座にも近い。メトロ銀座線に乗り換えられるのだから,ここからどこに向かうにしてもまずもって不便はない。港区の下町は田舎者にも居心地がいい。 その新橋駅構内の「かのや」。天丼セット,700円。今日初めての食事。中国人(たぶん)のお姉さん,今日は元気に働いていた。この人がいるとなんかホッとする。この店の看板娘だよね,もう。