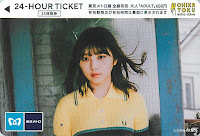● 川崎から東海道線で新橋。新橋からメトロ銀座線で三越前。今日はここを起点にして銀座線を行ったり来たりしようと思う。
● まずは,地下のタロー書房を覗くことから。老後の遊びとして外国語を勉強するのはありでしょ。英語とかフランス語とか中国語のようなメジャーな言語じゃなくて,超マイナーなやつ。書店に教本があるようなのはマイナー度が足りない。けど,ここから選ぶならビルマ語だな。 NHKの語学講座はもちろん,外語大学にコースがあるような言語は外した方がよさそうだが,そうなると他にどんな言語があるのかわからない。どうやって勉強すればいいのかもわからないな。
● 地上に出る。古河市兵衛の胸像がある。このあたり,何度か歩いていると思うのだけども気づかなかった。 行商から身を興し云々。明治の時代にはジャパニーズドリームがあったんですかねぇ。青雲の志という言葉が似合う時代だったのかなぁ。
古河グループという言葉もあるのだが,ググってみたら富士通がその1つなのだった。今でもグループとしての実態はあるんだろうか。
● 久しぶりに福徳神社。小さい神社だけれども,これあるために空間の質が上がっているのは間違いない。小さいながら地価を計算すればビックリするような額になるだろうところに,これだけの言うなら空き地を作りだしているのだから,大したものなのだ。 日本の場合はこういうところに神社があって,“憩い” を作る。ヨーロッパではとにかく広場を作る。教会を神社と対比しては間違うことになる。
● 日本橋でも最もハイソなこのエリアから神田が近い。江戸時代には日本橋は下町だったらしいのだが,人形町や浜町はともかく,このあたりはとっくに企業町になっている。っていうか,三井町だな。
 |
| 日本橋のハイソなエリア |
そこから神田まで歩いて数分というのが不思議な気がする。銀座と新橋の例があるじゃないかと言われれば,まったくもってそのとおりなのだし,わずかの移動でガラッと空気が変わるのが,東京を含む都市の魅力なのだと思うのだが,そうであっても不思議な気がする。
● ので,中央通り(国道17号)を神田まで歩いてみた。逆に辿れば日本橋から銀座を経て第一京浜になるわけだから,中央通りは文字どおりに中央通りなのだが,国道17号が中央通りなのは神田までで,ここから中央通りは17号と別れて上野広小路に至る。国道17号は本郷通り,白山通りとなって,霧の彼方に消えていく。 用があって神田に来たわけではないから,ここからまた銀座線に乗って銀座に戻ることにする。
● 銀座で何をしたかというと,G-SIXに行った。銀座にはわりと来る。伊東屋があるし,銀座LoFtがあるし,無印の旗艦店がある。多少とも文具好きなら,銀座はやはり特別な場所だ。 しかし,G-SIXに入ることは,ぼくはあまりない。特別すぎるからだ。特別すぎて気後れがする。よほどテンションが高いときでないと入っていく気力が湧いて来ない。
そのテンションは,たとえば着ている洋服,履いている靴,持っている鞄などによって影響される。今日はどうにかマトモな格好をしていたので,勇を舞して入ってみたのだ。
● 行くところは蔦屋書店しかない。ここはそのまま美術館だと思いたくなる。そういう形態でモノを商っている。 まず,文具がそうだ。万年筆が多いのだが,プラチナのキュリダスもあるものの,蒔絵や漆を施した,あるいは浮彫をあしらった工芸品とおぶしかないようなものが多く展示されている。
実用を満たせばいいという人はお呼びじゃないところだ。ここはおまえのような者が来るところではないと,商品が語っているのだ。臆してしまう。テンションを高めないと行けないところだというのは,そういうことだ。店が人を選ぶのだ。
● 常にいくつかの展覧会を行っている。今は,「京都のものづくり-KYOTO another story」が開催されている。「京都のこれからを担う,次世代の職人やアーティストが生み出す品々」を展示している。もちろん,売り物でもある。
漆塗りの自転車やサーフボードがある。待ちな,これは乗らないで飾っておくためのものか,と言いたくなるところだが,実際に乗りだすことができるのだろう。
● 上野裕⼆郎 新作個展「Surge/渦動」というのも開催されている。「私は主として生物をモチーフに,それらが持つ内在的な気や外界との揺らぎ,あるいは生成と消滅を繰り返しながら続いていく時間と物質の流れといったものに迫ることを自身の表現の主題としている」人なのだが,これもやはり人を選ぶだろう。
「ステンドグラスアーティスト・ひらのまり作品展示」も開催中。“クリームソーダ~不純喫茶ドープ” や “ゼリーポンチ~喫茶ソワレ” といった作品が展示されているのだが,それらがどんなものなのか。蔦屋書店のサイトを見ていただきたい。
 |
| 銀座の一番 |
● この場所でこれだけの広さを占めるのだから,テナント料を支払って黒字を残すためには,文庫本を1冊しか買わない人を相手にしているわけにはいかない。文庫本1冊のお客様も大事にしたいから,しっかり稼がなければならないのです,と言うのだろうけど。 たまに目の保養をさせてもらいたいものだが,かなり敷居が高いな。
次は,二度目の三越前。ただし,すぐに半蔵門線に乗換えて水天宮前。やはりね,隅田川を見たくなるんですよ。30分ほどボーッと川面を眺めた。
絶対,パリのセーヌ川よりいいっしょ。って,セーヌ川ははるかな昔に一度見ただけで,ほとんど記憶にはないんだけど。
● もうひとつ,東京シティエアターミナルを覗いてみたが,これは別途,記録しておく。 半蔵門線をひと駅乗って,清澄白河。深川になる。ここも何だかんだでけっこうな回数,来ていると思う。
隅田川を挟んで日本橋人形町,浜町とこちら側の深川。空気感はあまり変わらないと思う。下町的風情と言ってしまえばそれまでなんだけども,シャキっとした感じというか,眼を伏せない感じというか。
● ここから門前仲町までフラフラと歩いて,ユックリと,しかしガッツリと飲食いして,宿に帰って寝る。ということをやってみたいものだが,やりはしないと自分でわかっているのが,情けない。 高橋から小名木川を眺めて,少し歩いただけで帰ってきたけれど,この街はそういう対応の仕方をしてはいけない。腰を据えてかかるべし。
● どうしてこんなにマメに下車したのかというと,メトロ24時間券のモトを取ろうという発想から。身も蓋もないんだけど,それがある。動機が不純というか貧困というか。 が,そういう動機であっても,ともかく動くわけで,動いていれば瓢箪から駒が出ることもあるのではないか。動かないよりはいいだろう。
● 押上では東京ソラマチには寄らず,まっすぐ東武の南栗橋行きに乗りました。駅のホームにリンゴの自販機があって,売り方は色々あるものだなぁと感心した。売れているんだろうかな。 東武宇都宮駅に着いた。平日のオリオン通りを歩くことはまずないので,月曜19時のオリオン通りはどんなものかと思いきや,日曜の方が活気がある。月曜から飲む人はそんなに多くないのかね。