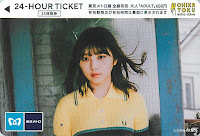● 有隣堂が You Tube で発信している「有隣堂しか知らない世界」は,小咄を聞いているようで面白く,時間も短いので,だいたいは見ている。複数回見ているのもある。
MCのブッコローが丸めようとしないところがいい。そういう方針で作っている。有隣堂の社員が話者として登場するのだが,業界や会社側に立つんじゃなくて,あなた個人を出してくださいという感じて作成しているようだ。
とはいっても,カットされるところもけっこう大量にあるっぽいのだが。まぁ,そりゃそうだろうね,と。
● で,今回は「神奈川あるあるの世界」。有隣堂の社員ではなく,「神奈川のあるあるを題材にしたコミック『#神奈川に住んでるエルフ』の著者である,鎧田(よろいだ)氏が登場」。
鎧田さん,若い(30代か)女性。職業は漫画家。
● この中で川崎がひどい言われようだ。ブッコローが,川崎は日本有数の工業都市で,駅周辺には商業施設もできて栄えているし,休日も大変賑わってますよねぇ,まぁ,だいぶ変わってきたんじゃないですかぁ,とジャブをかます。
鎧田さんに至っては,初めて川崎に来たときは地面が汚いと感じたとか,東急東横線では英語の本を持った人を見かけたが,南武線で本を持っている人を見たことがないとか,川崎に住むのは嫌だ,ラッパーがいそうで怖いとか,じつにストレートだ。
● それにブッコローが追い打ちをかける。幸せな人生とは南武線にどれだけ乗らずにすむかだ,と言いだす。
武蔵小杉や登戸など人口稠密なところを走るのに,短い6両編成。19~20時の乗車率は198%に達することもあるんだそうだ。
南武線は川崎市民のための路線だろうから,川崎市民である以上,幸せな人生は送れない。
● 小気味いいほどにこき下ろしている。ぼくは田舎も田舎,栃木の在に住んでいる者だから,はっきり他人事だ。
アハハハと笑ってみているのだが,川崎市民もそれを楽しんでいるのだろうな。その程度には成熟してますよ,と。
有隣堂だってそう踏んでこの動画を流している。だって,川崎にも有隣堂の店舗はあるんだからね。
● ちなみに,川崎との接点はミューザだった。何度かミューザに行くうちに,ミューザの隣に新しいホテルができて,そのホテルに泊まるようになった。
横浜は取り澄ました感じがするが,川崎はサッと入っていける。駅にしたって,横浜駅は巨大すぎる。川崎駅くらいでいいのだ。
● 横浜は誇り高き独立国だ。何に対して独立しているかというと東京に対してだが,横浜人は東京を一格下に見ているのではないかと思うことがある。
川崎はそんなプライドは持っていない。そもそも,行政区域としての川崎市はあるが,川崎市民はいない。川崎在住の新宿区民,渋谷区民,品川区民がいるだけだ。川崎市を縦断するのは難しいのだ。麻生区の住民にしたら,川崎区に行くよりは新宿に出る方がよっぽど世話なしだ。
これを別の言い方で表現すれば,川崎は開放的だ。外に対して開いている。閉じようがないのだ。そういうところは居心地がいい。
● かつては公害のイメージがあった。川崎病という言葉は,川崎にだいぶダメージを与えたろう。
現在にいたるも,風俗の街,ドヤ街,酔っ払いが多い,治安が悪い・・・・・・と思っている人が多いのではないか。駅西側が再開発で垢抜けたといっても,そこはそれ,川崎だからねぇ,と。
たしかに,川崎駅の東口を出ると,それっぽい印象を受ける。そして,そこが川崎の中心街なのだ。やっぱりと思ってしまうのだが,そういうエリアは大都市ならば必ずある。川崎の場合は,それが駅から見えるところにあるというだけだ。
風俗街である堀之内や南町も旧東海道から見えてしまう。もうちょっと奥まったところにあるとイメージはかなり違ってくるはずだ。しかし,よその大都市も奥まったところにあるだけのことで,あるのは同じだ。
● ただ,それだけのことなので,さほどに構える必要はない。川崎の開放的な雑踏を楽しめばよいと思う。
川崎に泊まって東京見物するのに何の支障もないし,川崎駅周辺には書店が多いことも知っておいた方がいいだろう。