● 宿泊している銀座のミレニアム三井ガーデン東京から晴海通りを見ると,けっこうな人が歩いている。これから仕事だよという人もいるだろう。っていうか,朝のこの時間帯ではそういう人が多いのかも知れない。
一方で,休日の銀座を楽しもうという人が集まっても来ているだろう。ここから見ていても,そういう人は見分けがつく。
一方で,休日の銀座を楽しもうという人が集まっても来ているだろう。ここから見ていても,そういう人は見分けがつく。
● コロナ禍でも4~6月の深刻期を脱して,だいぶコロナ以前に戻ってきた感がある。
欧州では第2波がやってきて,再びロックダウンに踏み切る動きがあるらしいが,どういう訳の訳柄か,日本(というより東アジア)では死亡者が少ない。
なぜそうなのか。それを説明する仮説も専門家から提出されているけれど,ともかく日本ではコロナをあまり深刻に考えない気風が一般化しつつある。
なぜそうなのか。それを説明する仮説も専門家から提出されているけれど,ともかく日本ではコロナをあまり深刻に考えない気風が一般化しつつある。
政府がGoToキャンペーンを打ちだしたときも,マスコミ報道を見る限りでは日本中こぞって反対なのかと思えたが,今はそうではあるまい。政府は正しかったと考える人が多くなっているのではないか。
● ぼくはもう現役を引退したので,釈迦のいう八苦のうち,怨憎会苦(会いたくない人に会わなければならない苦しみ)からは解放された。この世は苦だというとき,その苦の最大のものが怨憎会苦であることが,しみじみ了解される今日この頃というわけだ。
ので,ことさら気分転換を要することもないし,頑張った自分へのご褒美として東京のホテルに泊まるというのも当たらない。だいたい,ぜんぜん頑張ってないからね。
ので,ことさら気分転換を要することもないし,頑張った自分へのご褒美として東京のホテルに泊まるというのも当たらない。だいたい,ぜんぜん頑張ってないからね。
というわけで,申しわけないようなものではあるのだが,ぼくも東京を楽しもうとしている側の人間だ。
● 申しわけなさついでに,起床は9時近かった。10時までにチェックアウトしなければならないプランで泊まっているのだけども,1,500円追加して11時アウトにした。
東銀座から日比谷線で人形町に出た。22日にも同じようにしている。人形町に泊まると銀座に出たくなり,銀座に泊まると銀座以外に行こうとする。
東銀座から日比谷線で人形町に出た。22日にも同じようにしている。人形町に泊まると銀座に出たくなり,銀座に泊まると銀座以外に行こうとする。
正午近いのだが,かなり空いてるのは何でだ? この街に限らず,日曜日となれば,地元の人より地方からやって来た人たちの方が圧倒的に多いはずだ。地方にはファストフードのチェーン店しかないというのが実情だ。せっかく東京にいるんだから,地元にもある吉野家じゃなくて別のものを食べたいと思うのかもしれない。
が,隣のマックには行列ができている。よくわからない。
が,隣のマックには行列ができている。よくわからない。
● 水天宮前から半蔵門線をひと駅乗って,清澄白河にやってきた。門前仲町なら蛎殻町にあるホテルを定宿にしていた頃,隅田川大橋を渡って何度か歩いたことがある。その際,清澄庭園は見ている。
が,この駅で降りるのは初めてだ。東京はエリアによってくっきりと色合いが違う。駅前の清澄通りを歩くだけで,はっきり感知できる。さっきまでいた銀座とはまるで違う。
通りに面して建っている建物群がそう思わせる。高さの並んだ木造洋館(とは言わないのだろうが)が並ぶ一画があって,それが独特の空気を作っているのだ。
滝沢馬琴生誕の地でもあって,碑が建てられている。滝沢馬琴に限らず,けっこうな数の文人に所縁があるところだろう。
が,この駅で降りるのは初めてだ。東京はエリアによってくっきりと色合いが違う。駅前の清澄通りを歩くだけで,はっきり感知できる。さっきまでいた銀座とはまるで違う。
通りに面して建っている建物群がそう思わせる。高さの並んだ木造洋館(とは言わないのだろうが)が並ぶ一画があって,それが独特の空気を作っているのだ。
滝沢馬琴生誕の地でもあって,碑が建てられている。滝沢馬琴に限らず,けっこうな数の文人に所縁があるところだろう。
● 門前仲町もそうだけれども,ここもお寺が密集している。こんなにお寺ばかりでやっていけるのかと思う。兼業僧侶ばかりなんだろうか。にしては,それなりに立派なお寺なんだが。
っていうか,東京ってさ,高輪や白金台にも寺町と言いたくなるくらいのところがあるし,浅草は言うに及ばずで,東京は寺の街でもある。
っていうか,東京ってさ,高輪や白金台にも寺町と言いたくなるくらいのところがあるし,浅草は言うに及ばずで,東京は寺の街でもある。
常設展示の「江戸の町並み再現」が一番面白い。面白いというか,実物大で見せてくれているのでわかりやすいということ。
● 説明書きによると,江戸時代の日本人の平均身長は,男が155cmで女が145cmだったらしい。そのくらいが適正で,今は男も女も無意味にでかくなり過ぎているのではないかとも思う。
が,江戸時代というのはその前の安土桃山に比べても,日本人の身長が縮んだ時代らしい。
ということは,食に事欠くのがあたりまえの時代だったということか。あまり住んでみたいとは思わないね。ひと頃,江戸時代礼賛の風が強まったことがあったけれども,少し冷静になれというところですかね。
ということは,食に事欠くのがあたりまえの時代だったということか。あまり住んでみたいとは思わないね。ひと頃,江戸時代礼賛の風が強まったことがあったけれども,少し冷静になれというところですかね。
● 月見飾りの展示があった。月見団子は直径が10.5cmもあったんだそうだ。おにぎりよりもでかい。ご馳走を食べることのできる行事でもあったのだね。
十五夜(旧暦の8月15日)は中国伝来と認められるけれども,十三夜(旧暦の9月13日)を言祝ぐのは日本のみに伝わる風習とのこと。
十五夜(旧暦の8月15日)は中国伝来と認められるけれども,十三夜(旧暦の9月13日)を言祝ぐのは日本のみに伝わる風習とのこと。
● 「江戸のまんが展」も開催中。漫画という言葉がこの時期の史料に登場しているらしいのだが,現在の漫画とは当然異なる(今の言葉では戯画)。
じっくりと見ていけば,けっこう想像を刺激してくれるはずだと思うのだが,そのじっくり見るということ自体,誰にでもできることではないようだ。なぞるようにそそくさと見て,終わりにしてしまった。
じっくりと見ていけば,けっこう想像を刺激してくれるはずだと思うのだが,そのじっくり見るということ自体,誰にでもできることではないようだ。なぞるようにそそくさと見て,終わりにしてしまった。









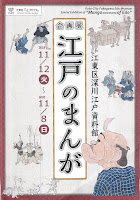

0 件のコメント:
コメントを投稿