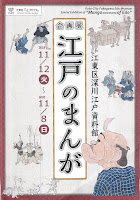● 半蔵門線の住吉駅で「メトロミニッツ」という月刊のフリーペーパーを発見。発見というのも何だけど,今まで気がつかなかったものでえ。
A4,本文38ページという堂々たるもの。スターツ出版が編集発行を担当しているが,発注元は東京メトロなのだろうね。
A4,本文38ページという堂々たるもの。スターツ出版が編集発行を担当しているが,発注元は東京メトロなのだろうね。
● 不思議なのはメトロの沿線はあまり出てこなくて,取材対象が日本全国に及んでいるところ。今月号では「Cycling in 茨城」というタイトルで水戸が紹介されている。
特集記事は New “フルサト” ツーリズム。「もう1つのふるさとを見つける旅に出ませんか? というご提案です」というわけなのだが。
特集記事は New “フルサト” ツーリズム。「もう1つのふるさとを見つける旅に出ませんか? というご提案です」というわけなのだが。
● New “フルサト”の定義は「生まれ育った場所でなくても,せわしない東京の日常に疲れた時にふと “帰りたくなる” 土地のこと」との由。
生まれ育った場所そのものではなくても,そこに近いところに住んでいる田舎人には関係のない話になる。
● ぼくもその口なんだけど,東京をNew “フルサト” にできればと思っているのだ。
田舎人の中には,東京の大学を出てUターンしてきたという人も多いと思うのだが,残念ながらぼくは東京に住んだことがない。が,東京の面白さ,いろんな面での濃密さというのは,若い頃から惹かれていた。休日にはしばしば出かけていた。
ただ,若い頃は点でしか東京を知らなかった。御茶ノ水なら御茶ノ水のこことここ,秋葉原なら秋葉原のこことここ,という具合に,点でしか知らない。点と点は脳内の地図上ではつながっていない。
● エリアというか街として知るようになったのは,わりと最近のことだ。年齢でいえば50歳を過ぎてから。そうして,街として(面的に)ふんわりと東京を知るようになると,東京以外の都市,たとえば京都,大阪,金沢,札幌,那覇に対する興味は急速に消えていった。東京だけでいいと思うようになった。
幸い,北関東のわが家から東京は近い。週末は東京で過ごすようになってきた。ぼくはもう “日常に疲れた時” を味わうことはないと思うが,日常に飽きることはしょっちゅうありそうだ。
そういうときに目先を変えるのに東京は絶好だ。充電するというと,今の自分には変な言い方になるが,そんな気分で出かけていく。
幸い,北関東のわが家から東京は近い。週末は東京で過ごすようになってきた。ぼくはもう “日常に疲れた時” を味わうことはないと思うが,日常に飽きることはしょっちゅうありそうだ。
そういうときに目先を変えるのに東京は絶好だ。充電するというと,今の自分には変な言い方になるが,そんな気分で出かけていく。
● で,週末の東京行きを繰り返した結果,東京をNew “フルサト” にできつつあるような気になっているのだけれども,そうなればなったで,東京に馴れてしまう。今までは刺激であったものが,刺激として機能しなくなる。
そうなっては少し困る。生粋の東京人はどうしているのだろう。東京があたりまえで,地方が新鮮に映るのだろうか。しかし,やはり東京にしか住めないと思い至るという流れになりそうではあるよなぁ。
● ぼくは東京には住めないと思う。週末に行くところにとどまる。経済的な問題は度外視しても,東京に住むだけのパワーはないと自認している。
現役を退いているから,満員電車に乗るなんて目には合わなくてすみそうだが,それでも東京の持つパワーに抗しきれる自信はない。New “フルサト” も基本は,遠きにありて思うものだ。
現役を退いているから,満員電車に乗るなんて目には合わなくてすみそうだが,それでも東京の持つパワーに抗しきれる自信はない。New “フルサト” も基本は,遠きにありて思うものだ。
● 自分のことを語りすぎた。「メトロミニッツ」の話だ。
基本は観光案内といっていいと思うんだけれども,丁寧に取材を入れている印象。格調高い誌面づくり。こういうのが無料で読めるんだったら,書店にあまたある旅行雑誌は要らないんじゃないかと思えてくる。
月1で出していたら,ネタ切れにならないのかと,余計な心配もしたくなる。定期購読したくなるが,電子版があってバックナンバーも読めるらしい。
基本は観光案内といっていいと思うんだけれども,丁寧に取材を入れている印象。格調高い誌面づくり。こういうのが無料で読めるんだったら,書店にあまたある旅行雑誌は要らないんじゃないかと思えてくる。
月1で出していたら,ネタ切れにならないのかと,余計な心配もしたくなる。定期購読したくなるが,電子版があってバックナンバーも読めるらしい。